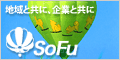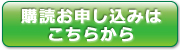創立100周年の柏崎信用金庫記念式典。これまでの歩みを振り返り、さ らなる発展を誓った=23日、柏崎エネルギーホール (2024/04/25)

柏崎市の子育て支援に役立ててほしいと、1千万円の目録を贈る入澤理事 長(左から2人目)=22日、市役所市長応接室 (2024/04/24)

市内愛好家が作ったつるし雛が飾られた座敷=市内新道の史跡・飯塚邸 (2024/04/23)
>>過去記事一覧
写真・記録集の刊行は、同会館の完成記念事業の一環として、2年がかりで編集作業が進められた。今から130年近く前、江戸時代の文久年間に難破・漂流し、シンガポールに日本人として初めて定住した漁民・山本音吉の紹介から始まる。
次いで、日本人社会の発展、日本人街、ゴム園経営、日本人小学校、日本人の暮らしと諸行事、神社・仏閣・教会、冠婚葬祭の様子など多角的にとらえた。往時を今に伝える豊富な写真、絵地図や査証などの資料、日本語・英語併記が大きな特徴だ。
この中で、柏崎出身の国際化の草分けとされ、現地で呉服商・越後屋を開業した故高橋忠平さんに関する「忠平と庫八ふたりの軌跡」「越後屋」は合わせて計20ページに及ぶ。数々の店舗の写真などが並び、当時の名店ぶりをしのばせる。
写真・記録集は日本人会の杉野一夫事務局長が企画し、当時現地のジェトロ駐在・三上喜貴氏(現・長岡技術科学大教授)を編集委員長に、多くの会員がかかわった。今回の製作のきっかけになった故高橋さん所蔵の「開かずのトランク」からぎっしり発見された貴重な写真・資料が大きな役割をになった。
出版記念会には、日本人会の招請で柏崎から市長、故高橋さんの孫で資料提供に協力した高橋忠行さんを含む研究会会員ら一行約20人が参列し、現地では柏崎出身の高原寿一・日本大使館公使らが歓迎した。交流の席上、同研究会が「トランクは置いて帰るので、(柏崎の)人物資料館に陳列する際に再び持って来てほしい」と再会を約束した。
写真・記録集はA4判約230ページ。問い合わせは同研究会世話人の小林進・市経済部長へ。
(1998/ 7/ 9)
※柏崎日報社掲載の記事・写真は一切の無断転載を禁じます。
すべての著作権は柏崎日報社および情報提供者に帰属します。新聞記事・写真など、柏崎日報社の著作物を転載、利用するには、原則として当社の許諾を事前に得ていただくことが必要です。掲載についてのお問い合わせは、お電話 0257-22-3121 までご連絡ください。