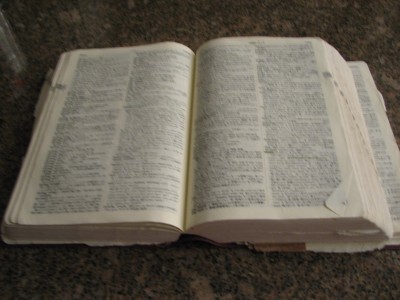今月使われているJavaScript-STARのメニューは?
私が使っているプロバイダーでは、自分のサイトをアクセス診断してくれるサービスがある。
どのページにどれくらいアクセスがあったかを調べては、時々楽しんでいる。
今は、多分、多くの大学で卒論やら修論の追い込みになっているのではないだろうか。
そこで、JavaScript-STARで何が使われているのかを調べてみた。
そうすると、一番は、相関係数計算で、二番はカイ二乗検定で、これらは他と1けた違う利用数だった。
学生、院生のみなさん、体に気をつけて、無事に書き終えられることをお祈りしております。
歴史上、やまなかった雨はない。
Good Luck!
どのページにどれくらいアクセスがあったかを調べては、時々楽しんでいる。
今は、多分、多くの大学で卒論やら修論の追い込みになっているのではないだろうか。
そこで、JavaScript-STARで何が使われているのかを調べてみた。
そうすると、一番は、相関係数計算で、二番はカイ二乗検定で、これらは他と1けた違う利用数だった。
学生、院生のみなさん、体に気をつけて、無事に書き終えられることをお祈りしております。
歴史上、やまなかった雨はない。
Good Luck!
ソフトウエア | - | trackbacks (0)